メッシです。
相場はトレンドとレンジの繰り返しですが、その多くはレンジ相場です。文献や話す人によって差異がありますが、トレンド相場は約3割、レンジ相場は約7割とも言われています。
では相場の大部分を占めるレンジとはいったいどんな状態を言うのでしょう?
今回はレンジ相場の種類や見分け方について判断や判定の仕方
を解説していきます。
※最後に確認テストがあります(^^)
目次
レンジ相場とは?
相場はレンジ相場とトレンド相場の繰り返しですが、圧倒的にレンジ相場が多いのが特徴です。
※トレンドについては初心者でも簡単にわかるトレンドとダウ理論についてをご覧ください
レンジというと”ある範囲内でレートが収まっている状態”を言いますが、言い変えれば”売りと買いが拮抗している状態”とも言えますね。
言葉だけではイメージが付きづらいのでチャートで見てみましょう。
インターネットでレンジを調べるてみると、上のようなチャートが比較的多く検索結果に引っかかる一般的なポピュラーな形です。
簡略図で書いてみると下のような図になります。
しかし、実際の相場で目にするレンジは毎回このようなわかりやすい形ばかりではありません。
レンジは形状やボラティリティよって色々な種類があるんですね。
では一体レンジの形状にどんなものがあるのか見ていきましょう。
レンジのパターンや種類とは?
レンジの種類といっても様々あって正確に細かく分類分けできるわけではないですが、カオスな相場をなるべくわかりやすく見るために大まかに種類分けしていきましょう。
※重要なのは相場を単純化してわかりやすく見る視点が必要ですので
レンジは”チャートパターン”と”ボラティリティ”の視点で種類分けができます。
チャートパターンから判断するレンジの形状
比較的よく見られる代表的な形として以下のようなものがあります。
・ボックスレンジ
・ペナント(三角持ち合い)
・フラッグ
・ボックスレンジ
サポートラインとレジスタンスラインといった水平線に挟まれたレンジ
(上のチャートと図を参照下さい)
・ペナント(三角持ち合い)
高値を切り下げ、安値を切り上げた三角形状のレンジ
・フラッグ
”下降フラッグ”と”上昇フラッグ”があり、右上がりのレンジと右下がりのレンジ
”下降フラッグ”(左)と”上昇フラッグ”(右)
下降フラッグはダウントレンドのリトレース(戻し)でよく見られ、上昇フラッグはアップトレンドのリトレース(押し)で見られる傾向にあります。
ボラティリティの違いによるレンジについて
レンジをボラティリティといった視点で見ると2つの種類があります。
・ボラティリティが低いレンジ
・ボラティリティが高いレンジ
ボラティリティは一般的に素早く大きくなり、ゆっくりと小さくなっていきます。
※ボラティリティについてはFXのボラティリティとは?をご覧ください
・ボラティリティが低いレンジ
ボリンジャーバンドがスクイーズ(収縮)していくと共にローソク足も短くなっていくレンジや、すでに狭くなったボリンジャーバンドの幅の中で横に流れているレンジがあります。
ボリンジャーバンドがスクイーズ(収縮)していくと共にローソク足も短くなっていくレンジ
すでに狭くなったボリンジャーバンドの幅の中で横に流れるレンジ
・ボラティリティが高いレンジ
ボラティリティの低いレンジと比べるとわかりやすいのですが、ローソク足も長くて上下に乱高下していますよね?
レンジの特徴とは?
・方向性が無い
・レンジを抜けると方向性がついて動き出す
などの特徴があげられます。
方向性が無い
全てのレンジで共通していることは売りと買いが拮抗しているので”方向性が出にくい状態”と言えます。
なぜならサポート付近では買いが入りやすくレジスタンス付近では売りが入りやすいため、一定の幅で収まる傾向にあるからですね。
レンジを抜けると方向性がついて動き出す
レンジを抜けると一気に方向性が生まれて勢いよく動き出します。
これはレンジ相場では方向感が無かった状態からレンジを抜けることで相場参加者がその方向に動意付くからです。
いわゆる”レンジブレイクアウト”と言われる状態ですね。
このようにレンジは様々な形があり、ボラティリティによっても性質が違います。
今回紹介したレンジが全てということではなく、相場は常に色々なチャートパターンを描きます。
まずは複雑に見えるチャートを単純化して見ることができるよう、水平線やトレンドライン、チャネルラインを引いてみてレンジを見つけてみましょう。
確認テスト
今回のレンジについての内容がしっかりと落とし込めているかどうか問題を解いてみましょう。
問題
①、②、④、⑤を穴埋めし、③は左と右のどちらかをを選んで下さい。
・レンジとはある範囲内で ① 状態を言いますが、
言い変えれば、 ② が拮抗している状態とも言えますね。
・下の図で上昇フラッグは左と右でどちらですか? ③
また、上昇フラッグは ④ の押し目の状態で見られます。
・レンジの特徴として、 ② が拮抗しているので ⑤ 状態
と言えます。
サポート付近では買いが入りやすくレジスタンス付近では売りが入り安いため、
一定の幅で ① 傾向にあるからですね。
回答
①レートが収まっている ②売りと買い ③右 ④アップトレンド ⑤方向性が出にくい
More from my site
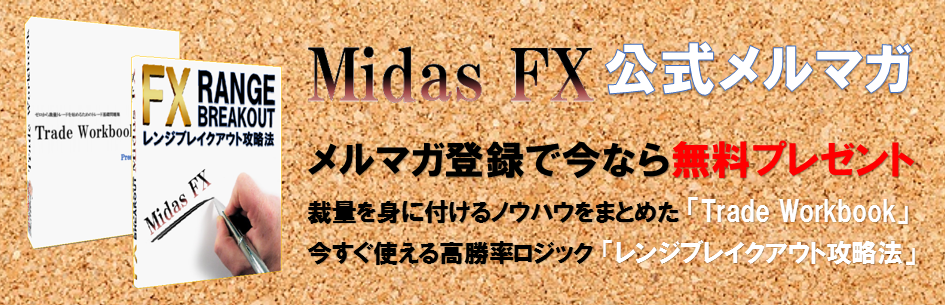
利益を上げ続けるために
逆算して身に付けていく3つのポイントとは?
Midas FX公式メルマガでは一つ一つポイントを絞ってわかりやすくお伝えしています
さらに「Trade Workbook」&「レンジブレイクアウト攻略法」で
より具体的なスキル(手法やマルチタイムフレーム分析力)を身に付けることが可能です
※「Trade Workbook」と「レンジブレイクアウト攻略法」は
メルマガ登録後すぐ手に入ります
Midas FX公式メルマガ登録【今なら無料】





























この記事へのコメントはありません。